業務内容
納品が完了した後は、正確な請求処理が行われます。伝票の内容と実際の納入実績を照合し、使用数量や単価、付随費用などを確認します。これらの情報をもとに請求書を作成し、発注者へ送付します。
請求は通常、月末締めでまとめて行うか、都度発行する方式が取られます。請求後は、入金状況を管理し、未収金が発生しないようにフォローします。また、請求に関する問い合わせや内容修正の依頼があった場合には、速やかに対応できる体制も求められます。

請求処理の役割は?
生コンクリートの取引は、製品の性質上「注文→製造→出荷→納入」までが迅速に行われる一方、事後処理である請求業務は慎重かつ正確さが求められます。請求内容にミスや遅れがあると、顧客からの信用を損ねたり、入金トラブルにつながったりする可能性もあるため、経理処理の中でも特に重要な工程の一つです。取引先との信頼関係を築くためにも、正確かつスムーズな請求処理が不可欠です。
Work flow
請求処理の流れ
納品データ・伝票情報の収集
請求書作成・発行
顧客からの確認と問い合わせ対応
請求内容の確定と締め処理
納品データ・伝票情報の収集
請求処理は、出荷実績や納品伝票に基づいて行われます。営業部門や製造現場から提出される情報を収集し、以下の内容をまとめます。
- 納入日・現場名・注文者名
- 配合種類、出荷数量、単価
- 割増料金(休日・夜間・緊急便など)の有無
- 返品やキャンセル分の控除内容
この時点での情報の正確性が、請求の基礎となるため、伝票と出荷データの照合作業が重要です。
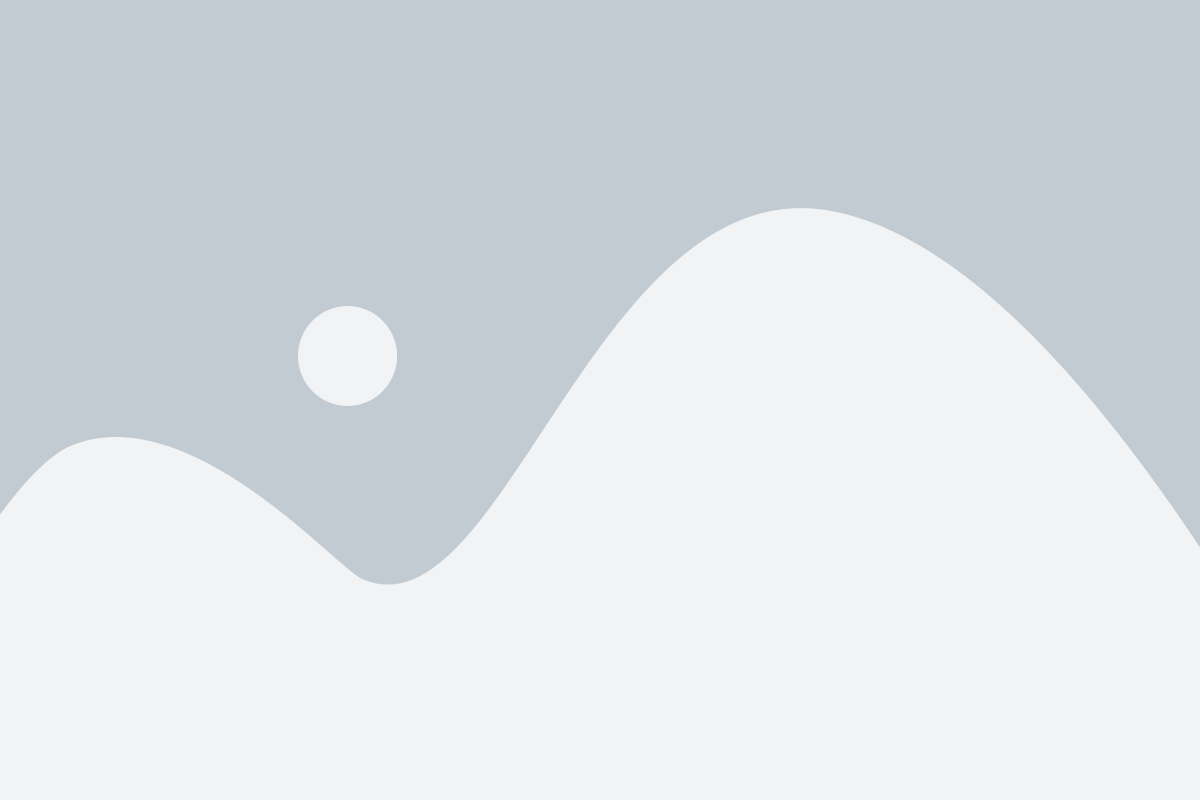
請求書の作成と発行
収集した納品実績をもとに、請求書を作成します。請求書には取引先情報、請求期間、明細(納入日・商品・数量・金額など)、消費税、合計金額を明記します。作成後は、担当者による確認を経て、発行・送付の手続きを行います。送付方法は、郵送、FAX、電子メール、取引先システムへのアップロード(?)など、顧客ごとの希望に応じて対応します。
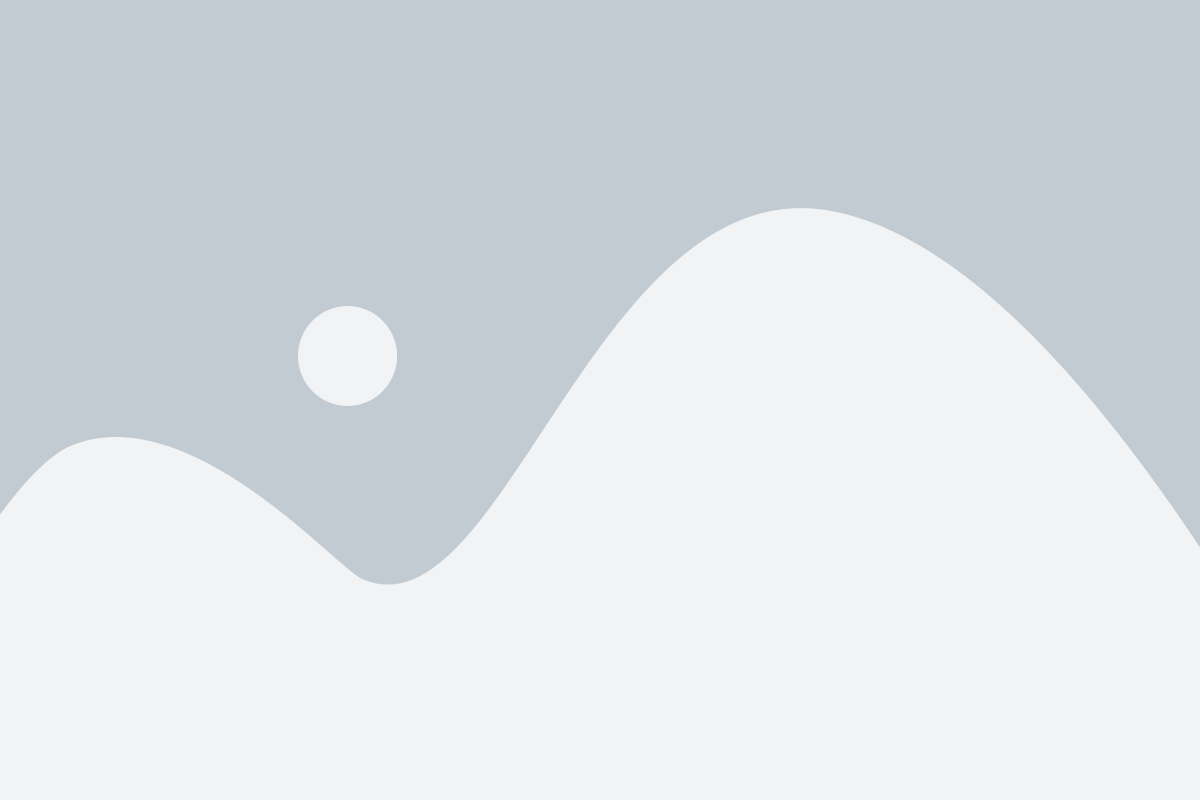
顧客からの確認と問い合わせ対応
請求書を送付した後は、顧客からの確認や問い合わせに対応します。以下のような問い合わせが想定されます。
- 数量・単価の違い
- 納品日や現場名の不一致
- 割増料金の有無についての確認
- 支払条件の調整依頼
不明点が発生した場合は、関係部署と連携し、事実確認を迅速に行うことで、顧客満足度を下げずに対応できます。
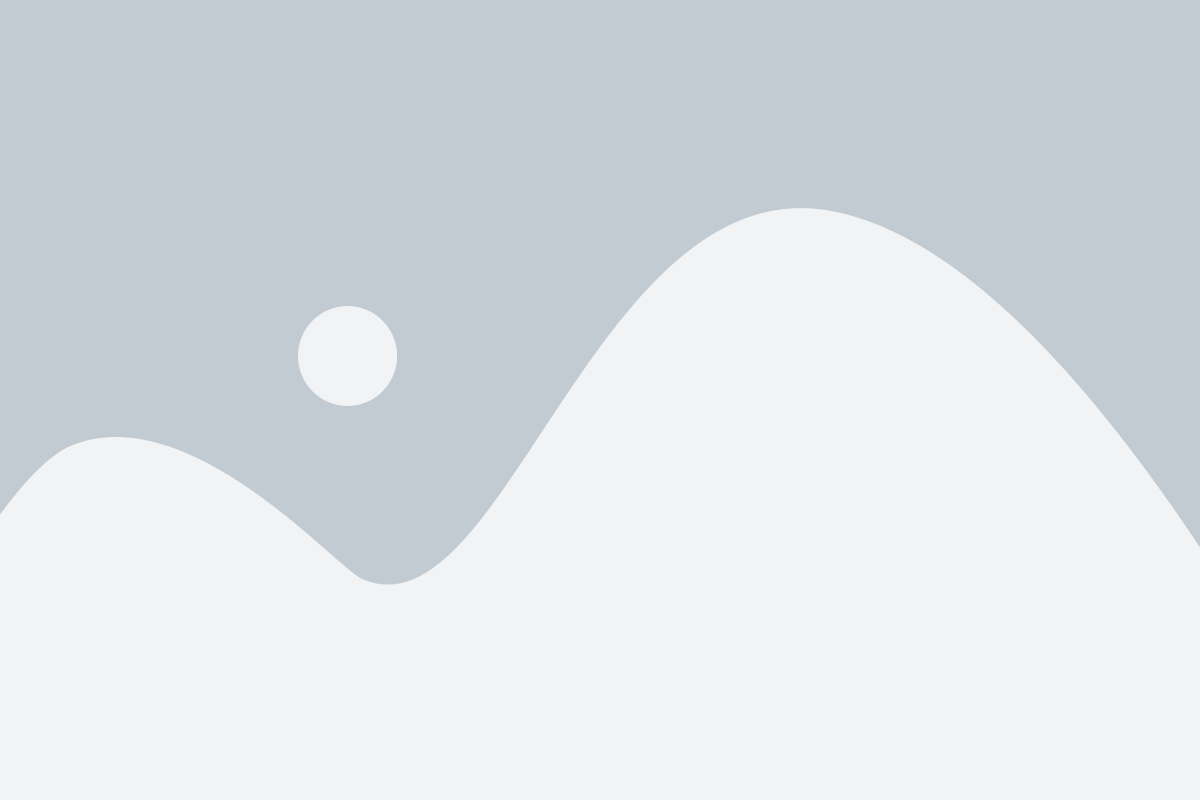
請求内容の確定と締め処理
>取引先ごとの締め日(月末・20日締めなど)に合わせて、請求書の最終確認と金額の確定を行います。締め処理後は、会計ソフトや販売管理システム(?)に請求情報を登録し、入金管理と連動できるようにします。また、請求書発行後の変更や再発行にも備えて、記録や控えを準備しておくことも大切です。
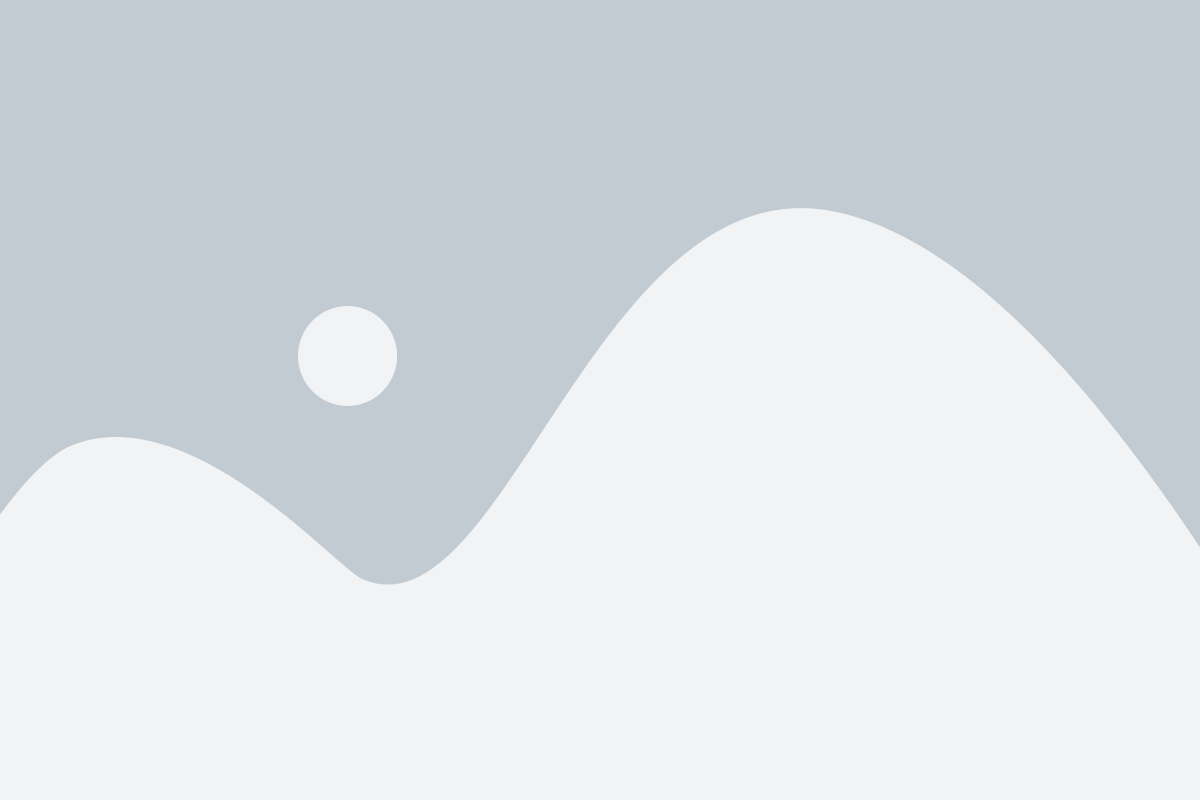
生コンクリートの供給において、請求処理は見えにくいながらも取引全体の信頼を支える重要な業務です。請求のミスが続けば、たとえ製品やサービスが良くても取引先の評価を下げてしまいます。だからこそ、正確・丁寧・迅速な処理と、問い合わせへの誠実な対応が、企業全体の信用力を高めることにつながります。日々の事務作業の積み重ねが、円滑な取引と安定経営の土台を築いているのです。